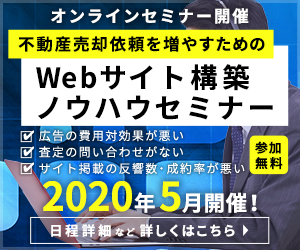不動産の土地を相続した場合は、相続税が課税されます。ここでは、相続した土地の税金の種類、土地の相続税の有無について、相続した土地の相続税評価額、土地の相続税を計算する方法、についてご紹介します。不動産の土地を相続した場合は、ぜひ参考にしましょう。

相続した土地の税金の種類
ここでは、相続した土地の税金の種類についてご紹介しましょう。
登録免許税
登録免許税は、所有権移転登記という相続した土地の持ち主の情報を登録する場合にかかる税金です。登録免許税は、固定資産税評価額に0.4を掛けたものです。
相続税
相続税は、被相続人の名義の土地を相続する際かかる税金です。相続税は基礎控除額以内の場合はかかりません。基礎控除額は、相続人数に600万円を掛けたものに3000万円をプラスしたものです。相続税を計算する場合は、トータルの遺産額が必要になります。トータルの遺産額としては、土地以外に株式や預貯金なども含まれます。また、債務の住宅ローンや借金というようなものも、財産のマイナスのものとして含まれるため注意しましょう。
トータルの遺産額としては、債務を預貯金や土地の評価額などのトータル額から差し引きして遺産として残ったもののトータル額になります。この際に、残額がマイナスあるいは0円であれば相続税は課税されません。
次に、相続税を計算する方法についてご紹介しましょう。例えば、夫が亡くなって妻と長男、長女が相続人、8000万円のトータルの遺産額 としましょう。この場合は、相続人が3人であるため4800万円の基礎控除額になります。そのため、課税遺産相続総額は8000万円から4800万円を差し引いた3200万円になります。
次に、妻と長男、長女で、3200万円の課税遺産相続総額を分けます。妻は3200万円に1/2を掛けた1600万円、長男は3200万円に1/4を掛けた800万円、長女は3200万に×1/4を掛けた800万円をそれぞれ相続します。なお、国税庁が決定している相続金額と税率、控除額は次のようになっています。
- ・相続金額が1000万円以下の場合は、税率が10%、控除額は0円
- ・相続金額が3000万円以下の場合は、税率が15%、控除額が50万円
- ・相続金額が5000万円以下の場合は、税率が20%、控除額が200万円
- ・相続金額が1億円以下の場合は、税率が30%、控除額が700万円
- ・相続金額が2億円以下の場合は、税率が40%、控除額が1700万円
- ・相続金額が3億円以下の場合は、税率が45%、控除額が2700万円
- ・相続金額が6億円以下の場合は、税率が50%、控除額が4200万円
- ・相続金額が6億円超の場合は、税率が55%、控除額が7200万円
このように、相続金額が大きくなるほど、税率と控除額は大きくなっています。そのため、妻は相続額が1600万円であるため税率が15%、長男と長女は相続額が800万円であるためそれぞれ税率が10%になります。それぞれの相続税の金額は次のようになります。
- ・妻の相続税の金額は1600万円に15%を掛けて50万円を差し引いた190万円
- ・長男と長女の相続税の金額は800万円に10%を掛けた80万円
つまり、相続額の金額としては、妻が190万円、長男と長女が80万円ずつであるため、家族としては350万円になります。
土地の相続税の有無について
基礎控除額よりも相続財産が少なければ、相続税は課税されません。一方、基礎控除額より相続財産が多い場合は、基礎控除額をオーバーした分にだけ相続税がかかります。被相続人が亡くなった時にいくらの財産であったかという時価に対して、相続税は課税されます。時価というのは、簡単に言えば、すぐにお金に換えるといくらになるかというものです。
株式や現金の場合は簡単ですが、不動産の場合は面倒です。そのため、誰でも財産の評価額が分かるように路線価を国税庁は決定しました。この路線価を使うと、土地の評価額は簡単に誰でも計算できます。
相続した土地の相続税評価額
土地の評価法としては、主として、実勢価格、固定資産税評価額、相続税評価額があります。土地を評価する場合は、相続税評価額が使われます。相続税評価額を計算する方法としては、倍率方式と路線価方式があります。なお、評価額は、次のような土地の場合は減額されます。
- ・いびつな土地
- ・大きな地積規模の宅地
- ・借地権の土地
- ・貸宅地
- ・貸家建付地
- ・セットバック、私道
- ・がけ地などがある宅地
ここでは、節税効果が大きくなる貸家建付地の場合についてご紹介しましょう。貸家建付地というのは、貸家のための宅地、つまり、持っている土地に建てた家屋を賃貸している場合のことです。代表的なケースとしては、賃貸アパートなどがあげられるでしょう。収益性が賃貸アパートは期待できますが、地域によっては賃貸アパートが供給過剰になっているため収益性があまり期待できないことがあります。そのため、節税効果のみでなく、収益性が事業として期待できるかを厳しく判断する必要がありますね。
貸家建付地の相続税評価額は、自用地の価額から自用地の価額に借家権割合と借地権割合と賃貸割合を掛けたものを差し引いて計算します。ここでは、貸家建付地の相続税評価額を、次のようなケースについて計算してみましょう。
- ・40万円の相続税路線価
- ・100㎡の敷地面積
- ・30%の借家権割合
- ・40%の借地権割合
- ・200㎡のそれぞれ独立した箇所の合計の床面積
- ・180㎡の課税時期に賃貸しているそれぞれ独立した箇所の合計の床面積
自用地の価額は、相続税路線価に敷地面積を掛けて計算します。この場合は、40万円に100㎡を掛けた4000万円が自用地の価額になります。賃貸割合は、課税時期に賃貸しているそれぞれ独立した箇所の合計の床面積をそれぞれ独立した箇所の合計の床面積で割って計算します。この場合は、180㎡を200㎡で割った90%が賃貸割合になります。そのため、貸家建付地の評価額は、4000万円から4000万円に30%と40%と90%を掛けたものを差し引いた3568万円になります。

土地の相続税を計算する方法
土地の相続税を計算する場合は、土地のみで計算しないで、基礎控除額を相続財産から差し引いて、相続を法定相続分通りにしたものとしてトータルの相続税額を計算します。相続税は、トータルの財産額から相続税法で決定されている基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は、3000万円に相続人数に600万円を掛けたものをプラスしたものです。
それぞれが納める相続税額は、実際に相続した比率によって計算します。例えば、トータルの相続税額が500万円の場合は、実際に相続した比率によって計算しますが、比率は妻が6割、それぞれの子供が2割ずつになります。相続税は、トータルの相続税額に相続する比率を掛けて計算します。そのため、相続税としては、妻が300万円、それぞれの子供が100万円になります。
相続税が配偶者はかからないということを聞くこともあるのではないでしょうか。配偶者は課税される場合が多くないということはありますが、実際には認識としては間違っています。配偶者の場合は、税金が少なくなる配偶者控除という制度があります。被相続人の配偶者は、実際に遺産分割などによって獲得した財産額が法定相続分の場合は、税金が課税されないようになっています。また、財産額が法定相続分をオーバーする場合でも、税金は1億6,000万円までであれば課税されません。